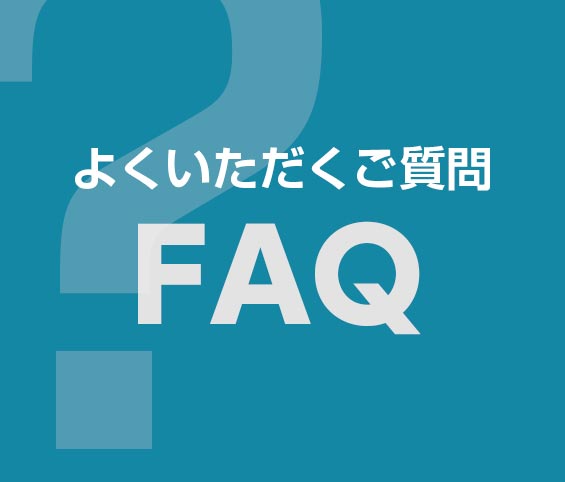研伸館プライベートスクールの講師は、京都大学・大阪大学・神戸大学・大阪公立大学の学生を中心としています。大学合格を目指す受験生を指導するにあたり、同じ関門を突破した経験が役立つことは言うまでもありません。講師たちは研修により日々研鑽を積んで授業に臨むとともに、マナーを備えた「人間力」の向上につとめています。

森川 正樹
京都大学 工学部(畝傍高校出身)
「何がわからないのかを探ること」を大切にしています。「何がわからないのかわからない」このような生徒は意外に多いです。今、学ぼうとしている内容よりもっと前の内容で詰まっていることも多いです。その生徒にとって、この問題を解くために何が必要なのか、何がわかればこの問題が解けるようになるのか、という点を常に生徒のリアクションを見て、探りながら授業を進めています。そのわからない根本的な部分を生徒が理解できる言葉まで噛み砕いて伝えるようにしています。

生徒の声 帝塚山中学校 2年
先生に教えていただき、小テストで点数が取れたり、定期テストの点数が上がっているので、実力がついていることを実感できています。また、大学受験についての話も教えてくださるので、とてもありがたいです。
指導例① 高1生・数学
- 研伸館の集団授業のフォローを進めつつ、定期テスト前は学校内容の指導をしています。元々、数学も好きで理解力も高いので、難しめの問題演習を中心に進めています。解説するときは、考えさせる余地を残すため、必要以上に丁寧な説明は敢えて避けて指導しています。また定期的に大学入試の問題にも取り組み、目標との差を体感し、計画的にどのように差を埋めていくのかを話しています。定期テストではコンスタントに9割、模試でも全国で上位の成績をキープできています。
指導例② 中3生・理科
- 定期テストの成績向上を目的に指導しています。自習時間は十分確保できているが、その割に成績が上がっていない様子でした。わからないことを理解するために努力していたのではなく、丸暗記で解決しようとしていたことが原因です。まずは、どの部分から理解できていないのかを調べ、そこに丁寧に時間を割いて説明し、学校の内容へと繋げていきました。少しずつですが、勉強の仕方がわかるようになり、平均点を超えるようになりました。

大下田 碧
大阪大学 工学部(兵庫県立宝塚北高校出身)
生徒の考え方を理解して修正していくということを大切にしています。問題を間違えるのは、何か考え方のずれが生じているからです。その箇所を見つけ出し、修正していくことで、正しい理解を導き出し、同じ考え方が使われている他の様々な問題にもアプローチできると考えています。また、積極的にコミュニケーションを図ることで、できるだけ生徒にとって楽しめるような授業になるよう心がけております。

生徒の声 神戸大学付属高校
私は数学の授業をとっています。答えを見ても分からない問題でも、先生に聞けば解法をすぐ分かりやすく教えて頂けます。
また、少しでも分からない所があれば初めから順をたどって何回も教えて頂けるので、1つ1つの問題が自力で完璧に解けるようになりました。とても親しみやすい先生で相談を受けてくれたり、談笑をしたり、授業がいつも楽しく、勉強を頑張る事ができています。
指導例① 中3生・数学
- 中高一貫校にお通いで、高校への内部進学に合格するために入塾されました。数学が苦手で、最初は問題の解き方にも抜けが多く見られましたが、なぜこの問題はこの解き方をするのかを意識して解説を行い、授業内容に沿った復習課題を毎回出しました。生徒さんご自身も真面目に授業に取り組み、課題もきっちりこなすことで、数学の力がつき、無事に内部進学に合格することができました。
指導例② 高2生・英語
- 大学入試に向けた英語指導をご希望で入塾されました。英語に対して苦手意識があり、高校英文法を総復習しています。英文法の中にも法則があり、他の単元と結びついていることも多くあります。その繋がりを意識し、整理したプリントを用いて授業を行なっています。単元学習後に行われる小テストでは、いつも高得点を取っており、英語に対する苦手意識を少しずつ取り払えているように感じています。今後は英文読解・長文読解指導に徐々に移行し、入試に向けた本格的な力を養成していきます。

岡嶋 康生
神戸大学 理学部(甲陽学院高校出身)
私が授業をする上で最も重視しているのは、基礎となる部分の理解です。例えば数学や理科の場合、どうしてこの場面でこの公式を使うんだ、と詰まってしまうことがあると思います。公式は、それがどのように導かれたのかを知らなければただの文字の羅列にしか見えません。そこを知るだけでも理解の助けになり、演習の際にも自分の頭で公式を導入しやすくなると思っています。

生徒の声 灘高校 3年
一人で勉強していた時は、全くついていけなかった学校の勉強に、先生に教えてもらい始めてから学校の授業の内容がわかるようになりました。勉強のペースを掴めるようになってから、平均点以上とれるようになりました。
指導例① 中2生・化学
- 学校の指導水準が高いため理解がなかなか追いつかない、と私立中学ではあるあるのお悩みをお持ちでした。まずは各分野で最低限必要となる項目を絞り、解説と演習を繰り返し行うことで基礎的な知識の定着を図りました。毎回実施する小テストの出来に応じて、もう一度同じ分野を演習したり、少しレベルの高い問題に挑戦したりと、臨機応変な指導を心掛けています。また、既習範囲に余裕が感じられた時などに学校内容の先取りを行っていると、生徒自身もアドバンテージを感じてくれたようで、それが学習意欲の向上にも繋がりました。
指導例② 高2生・数学
- 基礎的な問題は難なく解けてしまうものの、応用問題になると手が出なくなるタイプの生徒さんでした。そこでプライベートスクールの授業では、まず一緒に解説をなぞる時間を作っています。基礎的な問題と応用的な問題とで解法の共通している部分を提示し、どういった理由でその解法が使われているのかという部分の理解を促すように心掛けています。幸いにも生徒さん自身の学習意欲が高いので、演習量が十分に確保でき、回を追うごとに理解度が高くなっています。

井上 令子
京都大学 理学部(四天王寺高校出身)
私が授業で大切にしていることは、時間がかかっても「生徒が納得するまで何度も説明すること」、「生徒が自分の力で問題を解けるようになること」です。同じ内容を教えていても生徒一人ひとりにとって理解しやすい解き方・考え方は異なります。一つの説明で理解が十分にできなければ別の説明をして、生徒に納得してもらうことを心がけています。また、問題を解説するときは、ただ単に解き方だけを教えるのではなく、どのようにすればその解き方にたどり着くことができるのか、その過程を大切にして、単なる暗記ではなく、他の問題にも応用できる力が身に付くように意識しています。
指導例① 高2生・数学
- 学校の進度がかなり速いため、定期テストの成績向上を目標としています。問題集をテスト前に慌てて解くことがないように、学校の授業の進度と並行して進めるよう指導しています。授業ではその中で疑問に思った点を中心に解説しています。疑問点を残さないこと、既習の箇所がわからない場合はその都度戻って復習することを意識しています。今では数学の点数も上がり、さらに、数学に余裕が持てたことで全体の成績もコースの真ん中から、上位25%に入るようになりました。
指導例② 高1生・数学
- 学校の実力テストの点数アップを目標に入塾しました。定期テストは比較的簡単な問題がほとんどであるのに対し、実力テストでは応用的な難しい問題が出題されるため、定期テストでは高得点が取れるが、実力テストで点数が取れないというのが課題でした。そのため、普段の授業から学校では扱っていない少し難しい問題を演習することや、単なる解法の暗記にならないように考え方の道筋を丁寧に示すことを意識して指導しています。その結果、少しずつですが数学の点数が平均点を超えるようになってきました。

福島 瑠一城
大阪公立大学 商学部(岡崎高校出身)
私が授業をする中で大事にしているのは、生徒一人ひとりの学習スタイルや理解度に合わせた指導です。生徒の目標や苦手分野を把握し、適切なサポートを提供することで、自信を持って学習に取り組めるよう導きます。また、生徒とのコミュニケーションを大切にし、質問しやすい環境を整え、モチベーションを維持できるように努めています。

生徒の声 四天王寺高校 1年
福島先生はいつも具体的な例を交えて、わかりやすく説明してくださいます。
特に英単語を覚えるときにどういう時に、どのように使うのかの例のおかげでその単語のもつ意味がイメージしやすくなり覚えるのがそれほど苦痛ではなくなりました。
指導例① 高1生・英語
- 英語を学習する上で、その英単語や文法のイメージを持てるかどうかがかなり重要だと考えています。そのため、具体例や図を用いて教えることによってただひたすら暗記するのではなく、イメージを持たせやすいように心がけています。
指導例② 中3生・数学
- 数学は公式や定理を暗記するだけでは応用問題で全く対応出来ません。そのため私は、演習をまず生徒に実践させ、この公式をなぜこの演習では使うのかの理解と演習を解くことによる成功体験を積み重ねることで、問題を解くことへの自信をつけさせることを意識しています。

遊津 柊一
京都府立医科大学 医学部医学科(洛星高校出身)
授業で最も大切にしていることは「生徒とのコミュニケーション」です。学力向上のためには、問題を解く上で“どこがわからなくなったのか”、“なぜわからなくなったのか”をしっかりと究明する必要があります。授業では、私が解説をするだけでなく、様々な質問をたくさん投げかけることで、“わからない”を自分の言葉で説明してもらうよう意識しています。同時に、勉強の楽しさを知ってもらうことも大切にしています。勉強が好きになると自然に学習量が増えていき、成績も向上していきます。授業でのコミュニケーションをきっかけに興味のあることを見つけて、そこから少しでも授業が楽しかったと思ってもらえるように日頃から意識しています。

生徒の声 立命館高校 1年
数学の授業を受講していますが、数学に限らずその週での学校の疑問点やテスト勉強でわからない問題を質問をしても分かりやすく解説してくださり、テスト中に「あ!ここ先生に教えてもらったところだ!」ということが増えました。参考書の解説で全然理解できなかった問題も、私のつまづいている所に気づいてくださったり、もっと簡単に解く方法などを教えてくださったりで理解が深まりました。
指導例① 高1生・数学
- 数学の定期テスト対策を目的に指導を行っています。理解力は十分にあるものの、部活動が忙しく自学習に割ける時間が少ないため、解き方を忘れてしまうことが度々ありました。そのため、それぞれの解法に至る過程に重点を置いた授業を進めました。それにより解法を丸暗記するのではなく、解き方の引き出しが増え、期間が空いても一度解いた問題は確実に解けるようになりました。その結果、問題の数値を変えられたり捻った出題をされても解き切る力を養うことができました。
指導例② 高3生・数学
- 大学受験に向けた数学の指導を行っています。指導を始めた頃、数学が苦手という訳ではなかったのですが、定期テスト・模擬試験での得点にばらつきがありました。大きな原因は、得意分野と苦手分野がはっきりしていることでした。そのため、苦手分野の克服を最優先に授業を行い、基礎から徹底的に復習をし、演習を通して様々な考え方を指導しました。また、自学習で分からなかった問題は毎週の授業で必ず解決するようにも習慣づけました。その結果定期テストや模擬試験での得点が安定し、入試問題も解き切ることができるようになりました。

前田 早嬉
京都大学 工学部(洛南高校出身)
授業では「思考力を養うこと」を大切にしています。公式や解法をただ問題と紐づけて覚えるのではなく、“問題文の条件からどのようなことが言えるのか”、“答えを導くためには何が必要なのか”、解き始めるまでのアプローチをしっかり理解してから解き進められるようにしています。また、学んだことをどのように活かすことができるのかは、実際に解いてみることが大切です。まずは問題に対して自分なりに考えてみて、答えにたどり着かなかったときは、“なぜこの解法ではダメなのか”、“どうすれば足りない部分を補えるのか”、を一緒に解き進めながら見つけていきます。

生徒の声 洛南高校附属中学校 3年
学校の問題集やプリントで質問すると、どの問題もすぐに分かりやすく教えてくれます。授業がとても効率的で、時間を無駄にすることなく、しっかりと勉強を進めることができるので、日々の勉強の助けにとてもなっています。また、授業もとても熱心で、理解するまで繰り返し丁寧に説明してくれるだけでなく、どんなに小さな質問にも丁寧に答えてくれるので、問題を解ける楽しさを感じるようになりました。
指導例① 中3生・数学
- 数学の定期テスト対策を目的に指導を行っています。入塾時は、理解力は高いものの解き方を覚えることに重点を置いていました。そのため、まず習った公式の意味や用語の解説を行いました。その結果、ただ暗記するだけでなくイメージを持って理解してくれるようになりました。また、自分で考える時間を設けたり、模範解答の解法を使う理由を一緒に考えたりすることで、自分で問題文から必要な条件を予想して解答を導く力を養うことができました。
指導例② 高1生・数学
- 定期テスト対策を目的に指導を行っています。指導を始めた頃は、授業中に解けていた発展問題をテストでは解けなかったり、計算ミスで失点してしまったりが多く、実力を十分に発揮できていませんでした。原因分析をする中で、解き方を暗記してしまっている可能性が高いと考え、問題の目的が何なのか、そのために何の操作が必要なのかを一緒に考えながら解き進めて行きました。テスト前には分からない問題を一緒に全て消化し、万全の状態でテストに向かえるようになり、得点もアップしました。

森 彩仁
京都大学 経済学部(甲陽学院高校出身)
私が生徒指導の際に心がけていることは、知識のマッピングをお手伝いすることです。単に与えられた暗記事項を一つずつ、「点」として覚えるだけの勉強は、つまらないし面倒だと感じる生徒さんが多いのではないでしょうか。各知識を周辺情報や背景と繋げ、「面」として覚えられると、様々な事象の関わり合いが分かり、段々と新しい世界が見えてきます。これこそが、勉強の楽しさの一つだと私は思います。また、「面」としての暗記によって、ある情報を起点に芋づる式に周辺情報を引き出すことも可能です。頭の中の知識の「地図」が、楽しく、有用な学習に繋がるのです。私の指導がその一助となれれば幸いです。

生徒の声 甲陽学院中学校 2年
英語が苦手で、先生に基本的な所から教えてもらっています。
毎回の授業で丁寧に教えていただいている甲斐があり、少しずつですが英文法などが 理解できるようになりました。
指導例① 高3生・国語
- 1年ほど、大学受験に向けて、古文と現代文の演習を行いました。古文は、文法の復習を終えた後は、問題演習中心の授業でした。文法や単語を覚えていても、古典世界独特の風俗や文化を把握できておらず、文の内容を深く理解することが難しいときがありました。そこで、問題演習を通し、当時の人々がどのように考え、どのように暮らしていたのかを、様々な背景知識と共に紹介することを意識しました。現代文も、文章の読み方や作り方にとどまらず、筆者に主張の裏にある思想や主義もできるだけ紹介するようにしました。本人の努力もあって、無事に第一志望大学合格を果たしてくれました。
指導例② 高3生・英語
- 半年ほど、大学受験に向けて、英語の演習を行いました。単語や文法はある程度完成しているけれども、英文の論理構造や要旨を把握するのが、少し苦手であるように感じました。また、専門性の高い大学を目指していて、入試問題もその分野に関する専門的な文章から出題されていました。そこで、その分野に関する英文を論文等から抜粋し、読解演習する授業を行いました。筆者の主張に繋がるまでの、文章全体の大きな流れを、正確に把握できることと、その分野特有の知識を、ある程度頭に入れておくことを目標としていました。本人の努力もあって、無事に第一志望大学合格を果たしてくれました。

石田 舜
奈良県立医科大学 医学部医学科(東大寺学園高校出身)
私が生徒指導において最も重要視していることは、「生徒のどんな質問も受け入れること」「生徒が納得いくまで何度でも説明すること」です。個別指導では、生徒との距離が近いので、学校の授業や集団の授業では聞きにくいようなことも気軽に質問することができます。そのため、生徒が質問しやすいような環境作りに努めることが大切だと考えています。また、生徒が本当に理解できるまで徹底的に解説することも心がけています。理解できるまでのスピードは生徒によって異なるので、生徒一人一人に応じて指導法を調整しています。「分かった!」という感覚の楽しさを一人でも多くの生徒と共有できたら嬉しいです。

生徒の声 奈良学園高校 3年
私は、高1の秋から先生の授業を受け始めました。昔から英語が一番苦手だったのですが、今では一番得意な教科です。それは、先生が決めてくれたカリキュラムや勉強方法のおかげです。授業では、英文の構造やわからない構文・語法・文法について、毎回わかりやすく説明してくださいます。英語についてだけでなく、他の科目や受験の相談に乗ってくださることもとてもありがたいです。
指導例① 高3生・英語
- 難関国公立理系学部志望です。授業では主に英単語、英熟語の小テスト、英文解釈、長文読解に取り組んでいます。英文解釈、長文読解の力を向上させるには、単語、熟語量を増やす必要があるので、毎週必ず小テストを実施し、合格点に満たなかった場合は翌週に再テストを行っています。英文解釈では「この構造があるからこういう訳になる」というように、構造を確実に捉えることを強調して授業しています。結果として、模試での和訳問題での得点率が飛躍的に向上しました。長文読解では、まずは精読し、わからない単語や文の構造等を一つひとつ理解しながら解き進めるように指導しています。「英語は単語量に比例して長文読解の力も付いてくるので、受験直前まで伸びる科目」ということを常に生徒と共有しながら授業しています。
指導例② 高2生・数学
- 学校の成績向上を目標に授業しています。授業の初めに必ず、学校で習ったこと、宿題等で分からなかったことがないか聞くようにしています。分からなかったことを放置してしまうと、定期テスト直前になって焦ってしまうので、疑問はその都度解消するように指導しています。また、私立の高校では授業進度が速く理解が追いつかない場合があるので、塾では予習を進めて、少しでも学校の授業の理解度を上げられるようにしています。定期テストでは問題数が多く、時間も短いため、解答のスピードと計算の正確性が求められます。そのような定期テストに対応するため、毎授業で時間制限付きかつ計算量多めの小テストを実施しています。また、計画的に学習することで定期テストの成績向上が見込めるので、生徒と一緒に学習計画をたて、1週間のうちにやるべき範囲・単元を毎授業で決めるようにしています。